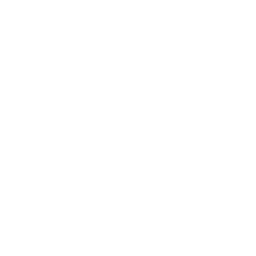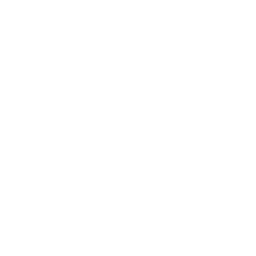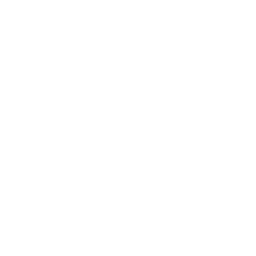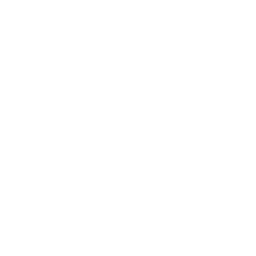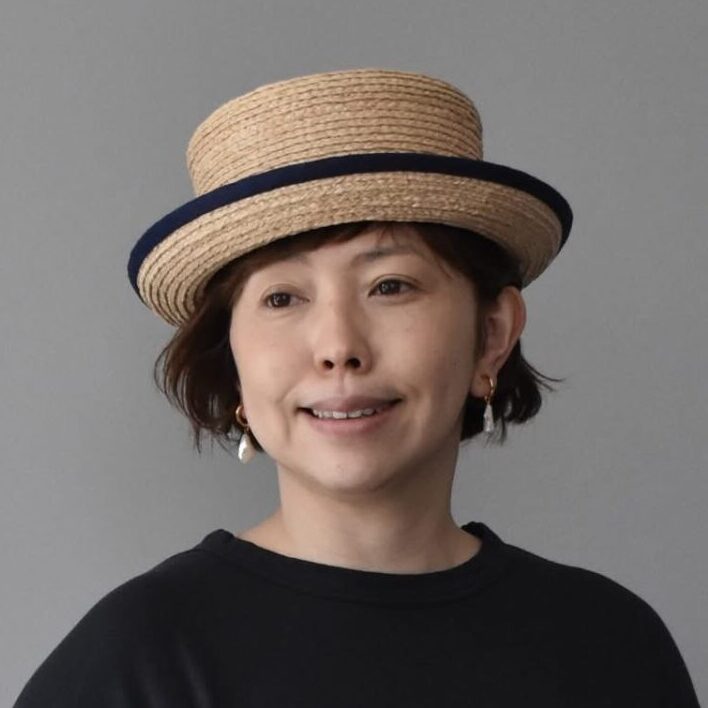
ふれて光る真鍮、ふれずに深まる真鍮——観光地のレリーフに見る銅合金の美しさ
北海道・函館にある五稜郭公園を歩いていると、松の木々のあいだから、ひとつのレリーフが姿を見せます。
それは、五稜郭の築造に尽力した人物・武田斐三郎の顔をかたどったもの。
春には桜が咲き、秋には落ち葉が舞うその場所で、今も変わらず訪れる人々を迎えています。
近づいてみると、顔だけが、不思議なほど光を帯びているのが目に入ります。
まわりの表面はやわらかな緑青をまとっているのに、そこだけは艶を保ち、金属の地肌がのぞいています。
その光は、長い年月のなかで誰かがふれた手の跡。思いがけず磨かれて、今の表情を見せているのです。
額をなでると、頭がよくなる——そんな言い伝えも
このレリーフには、「額をなでると、頭がよくなる」というちいさな言い伝えがあります。
観光のガイドブックには載っていないような話ですが、旅先で誰かが語り、誰かが聞いて、静かに広まってきました。
修学旅行で訪れた学生が写真を撮る前に手をのばしたり、
受験を控えた子どもに「触ってごらん」と声をかける家族の姿があったり。
そんな風に重ねられていった手のひらの記憶が、いまの光をつくっています。
モニュメントやレリーフで見かける“光る顔”
こうした光景は、五稜郭公園だけのものではありません。
旅先の観光地や歴史的な広場、街角の記念碑など——
多くの場所で見かける銅像やレリーフの顔や手のひらが、部分的に輝いているのに気づいたことはありませんか?
まわりは緑青やくすみをまとっているのに、なぜか鼻先や頬、指先だけが金色に光っている。
それは、誰かがふれたあと。
「触るとご利益がある」「願いがかなうらしい」「なんとなく触りたくなる」——
そんな理由で手をのばした人の数だけ、そのモニュメントには記憶が積み重ねられているのです。
銅合金が見せる「ふれた分だけ、光る」という変化
こうしたレリーフやモニュメントの多くに使われているのが、青銅や真鍮などの銅合金です。
銅を主成分とする金属は、空気にふれるとゆっくりと酸化が進み、やがて深い色合いをまとっていきます。
この自然な変化を「経年変化(けいねんへんか)」といい、素材が時間のなかで味わいを増していく様子が魅力のひとつです。
ところが、そこに人の手が何度もふれると、摩擦や皮脂によって酸化膜が削られ、内側の金属が現れます。
その部分だけが再び光を放つようになる——まるで自然に磨かれたように。
この「ふれた分だけ、光る」という変化は、銅合金ならではの美しい反応。
無意識のふれあいが、時間をかけてモニュメントの表情を変えていくのです。
モニュメントに銅合金が使われる理由
屋外に設置されるモニュメントに、銅合金がよく使われるのには、いくつかの理由があります。
- 控えめで上質な金属の光沢
- 人物や動物など、繊細な造形を表現できる加工性
- 錆びにくく、雨風に強い耐久性
- 時を重ねるごとに深みを増す風合い
- 人のふれあいで自然に磨かれ、唯一無二の表情が生まれること
ただきれいなだけではなく、ふれられることで変わっていく金属。
それは、時間と人の気配をたしかに受けとめる、あたたかな素材とも言えます。
chicoriの真鍮表札——ふれずに育てる、もうひとつの美しさ
chicoriがつくる真鍮の表札も、同じく銅合金のひとつである真鍮を素材にしています。
けれど、その育ち方はモニュメントとは少しちがいます。
表札は、家の顔として玄関に設置されるもの。
多くの人が触れる機会は少ないものの、かえって手あとが目立ちやすくなることがあります。
とくに、郵便受けやインターホンの近くにあると、無意識のうちにふれられてしまうことも。
そのため、chicoriでは「ふれずに育てる」ことをおすすめしています。
風や光、雨、湿度——自然のめぐりのなかで、真鍮は少しずつ落ち着いた表情に変わっていきます。
やがて、つやをおさえた深い色合いが現れ、住まいにしっくりとなじんでいく。
それが、もうひとつの美しい育ち方です。
ふれて光るモニュメント、ふれずに深まる表札
観光地で出会うモニュメントは、人の手にふれられながら輝きを増し、時間とともに表情を変えていきます。
手のひらの数だけ、そこには祈りや記念の気持ちが宿っているようにも思えます。
いっぽう、chicoriの真鍮表札は、ふれられることを前提とせず、自然のままに育っていく美しさを大切にしています。
雨や風とともに静かに色を変え、いつしか家にとけ込むような存在へと育っていく——
その穏やかな変化こそが、真鍮という素材が語るもうひとつの魅力です。
ふれることで光る。
ふれずに深まる。
どちらの姿も、銅合金という素材がもつちからと、時間がつくり出す本物の美しさを物語っています。