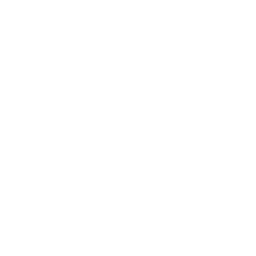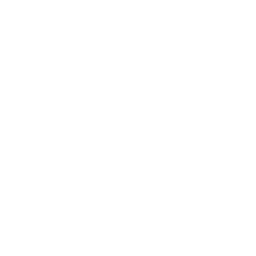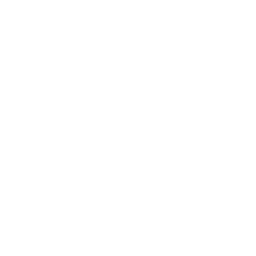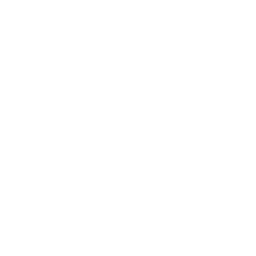真鍮はなぜ楽器に使われる?音を支える素材の力
日々真鍮という素材に触れる中で、その魅力や表情の変化には常に驚かされるものがあります。ただ、これまで「音を出す道具」としての真鍮にはあまり意識が向いていませんでした。実の兄が小学生の頃からトランペットを吹いていて、今も交響楽団などで年に数回演奏しているため、金管楽器に真鍮が使われていること自体は知っていました。しかし「なぜ真鍮なのか?」という点までは考えたことがなかったのです。今回あらためて調べてみて、素材としての真鍮と音との関係には、非常に奥深い理由があることがわかりました。

真鍮が使われる代表的な楽器とは?
真鍮はトランペットやトロンボーンなど、金管楽器の主要素材として古くから使われてきました。
兄が吹いていたトランペットも、もちろん真鍮製
私自身は演奏の経験がありませんが、兄がトランペットを吹いていたこともあり、真鍮が金管楽器に使われていることは自然と認識していました。当時は学校所有の楽器を使っていたため家に楽器があったわけではありませんが、演奏会などで見かけるあの金色の輝きが真鍮によるものだと知ったときは、妙に納得した記憶があります。
金管楽器以外にも使われている
クラリネットやフルートのキー部分、打楽器の一部パーツなど、管楽器以外でも真鍮が使われています。音の伝達や耐久性といった面で、部分的に真鍮が適しているとされているようです。
真鍮が音に与える影響とは?
真鍮はただの金属ではなく、音のキャラクターそのものを決める「音をつくる素材」だということがわかりました。

柔らかさと明るさが両立する
銅と亜鉛の合金である真鍮は、その配合バランスによって「音の柔らかさ」や「明るさ」が調整できます。兄の演奏を聴いていても、芯のある音ながらどこか温かみのある響きが印象に残っており、それが素材の力だったのかと思うと新たな発見でした。
響きが豊かで遠くまで届く
真鍮は音の振動をよく伝える性質があり、少ない力でも音が大きく広がります。中学時代、自分が野球部で練習しているときに、吹奏楽部のトランペットの音が外に向かって遠くまで響いていた記憶があります。あの「届く感じ」も、素材がもつ力によるものなのかもしれません。
真鍮と他の金属素材との違い
楽器には銀やニッケルなど、真鍮以外の金属も使われていますが、それぞれに音の個性があります。
銀やニッケルとの音色の違い
銀製の楽器はやわらかく深みのある音、ニッケルはやや硬く明瞭な音が特徴とされます。真鍮はその中間に位置し、柔らかさと輝きを兼ね備えているため、ジャンルを問わず幅広く使われているようです。
メンテナンス性と経年変化も魅力
真鍮は加工がしやすく、微細な調整や修理が可能なため、演奏現場でも扱いやすい素材です。無塗装仕上げの楽器では、時間とともに酸化が進み、表面に深みのある風合いが生まれてきます。一部の奏者や職人の間では「使い込むうちに音色が変わる」と感じる人もおり、そうした変化も含めて真鍮という素材の魅力なのだと受け取っています。
真鍮だからこそ出せる音がある
楽器の音は、演奏技術だけでなく「素材」によっても形づくられているのだと実感しています。

奏者の感覚に自然に寄り添う
真鍮製の楽器は、息の流れに対して素直に反応すると言われています。演奏者が表現したいニュアンスに素材が自然と応えてくれることで、音に一体感が生まれるという話もありました。
音も「育っていく」素材
時間とともに真鍮の見た目が変化していくように、音にもわずかながら変化が現れるという話があります。こうした経年変化を楽しみながら、長く付き合っていける素材であるという点も、真鍮の大きな魅力だと感じています。
まとめ
真鍮が楽器に使われていることは、兄の影響で以前から知ってはいたものの、その背景までは正直深く考えたことがありませんでした。今回あらためて調べてみて、音の響き、加工性、演奏性、経年変化までも含めて、真鍮という素材が「音を生み出すために選ばれている理由」に納得しました。普段はインテリアや表札など、静かな存在として見ていた真鍮ですが、「音を鳴らす」というもう一つの顔に出会えたような気がしています。
chicoriの真鍮表札

仕様 サイズ:M 150×150×3(mm) 材質:真鍮3㎜ 文字:エッチング凹黒染め ベース:バイブレーション仕上
chicoriの真鍮表札は、古来より受け継がれる伝統のエッチング加工技法で、薬品により文字をくぼませて刻み込んでいます。 この技法により、表面的な印刷とは異なる深みのある質感が生まれ、文字が剥がれる心配もありません。 真鍮ならではの経年変化により、年月と共に味わいが増す逸品です。 繊細な輝きを放つ真鍮の板にお名前や屋号をお入れします。